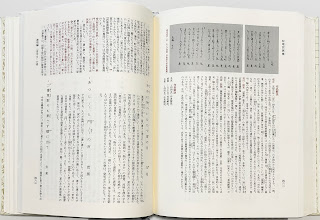高瀬梅盛『俳諧類船集』(1677年刊)
今回は「寄合」がどのように俳諧(連句)に引き継がれていったか、また松尾芭蕉はどのようにこの技法を扱ったかという話をします。
「寄合」から「付合」へー『俳諧類船集』
俳諧は西暦1500年頃に連歌から分離していくのですが、「寄合」の技法は俳諧にも引き継がれます。しかし連歌と俳諧では材料として使う用語も表現する世界も違うので、俳諧独自の寄合集が必要になってきました。たとえば1645年に松江重頼が刊行した『毛吹草』は俳諧創作のためのマニュアル本ですが、中には寄合を集めた章も含みます。
そのような背景のもと、画期的な集が刊行されました。1669年に京都の高瀬梅盛が著した『便船集』、そして1677年にその全面増補改訂版として同じ梅盛が刊行した『俳諧類船集』です。
『俳諧類船集』は連歌の寄合集とは若干性格が違うものになっています。まず収録される題が歌語に限定されず、俳言の範囲まで拡張されて増え、見出し題が『連珠合璧集』は886だったのが、『俳諧類船集』では約2700題に達しています。また『連珠合璧集』はあくまで文学の中での連想語を示すものだったのに対し、『俳諧類船集』は各題に解説を加え、時には歴史・民俗・博物を語る辞書的な要素を持たせています。
もう一つ大きな相違点は、連歌で「寄合」と呼ばれていたものが俳諧では「付合」と名称が変わっている点です。そのため『俳諧類船集』は「寄合集」ではなく、「付合辞典」「付合語集」などと形容されます(連句では次の句を付けること自体も「付合」と言うのでややこしいのですが)。「日本国語大辞典」では寄合と付合の違いについて
寄合が用語、題材など形式的なものに関係があるのに対して、(付合は)もっと広く情趣、心情など内容的なものまでをさす。
と説明しています。これだけだといま一つわかりにくいですね。後で実例を見ながらあらためて検討します。
『俳諧類船集』の一項目、「納豆」を引用してみましょう。
納豆[ナトウ]
汁 観音寺 浜名 寺の年玉
作善の斎非時一山の参会などの汁は無造作にしてよし。浄福寺の納豆はことによしとぞ。念仏講やおとりこしや題目講はめんめんの思ひ思ひの信仰なり。
そもそも「納豆」という大衆的な食物は、連歌で使われることはありませんし、連歌寄合集にも出てきません。いかにも俳諧的な主題です。付合語(寄合)として挙がっているのは、「(納豆)汁、(滋賀の)観音寺、(浜松の)浜名納豆、寺の年玉(年始のふるまい)」の4つです。さらに解説が加わり、「法事のときや寺の食事では納豆汁は簡単に作って良い。奈良の浄福寺の納豆はとくにうまいそうだ。念仏講、浄土真宗の報恩講、日蓮宗の題目講では納豆汁が振る舞われるが、それぞれの信仰に基づくものである」と書いてあります。これを見ると、江戸時代の関西における納豆文化がよくわかり、貴重な民俗資料ともなっています。
芭蕉はどのように付合を利用したか
芭蕉は実際の連句でどのように「付合」を用いていたか、作品に即して見ていきましょう。ここで例とするのは、1679年、芭蕉が36歳の時の作品「見渡せば」の巻です。桃青と名乗って談林の影響下にあった時代で、後年の蕉風連句とは趣が異なります。小西似春、土屋四友との百韻連句で、この2人が関西に行脚するにあたっての送別吟でした。四友は脇句のみを付けていて、実質的には芭蕉(桃青)と似春の両吟です。百韻という長い作品なので、付合に関係するところを拾い読みしましょう。付合は『俳諧類船集』に準拠して判断します。(以下類船集と略記)
連句の鑑賞に付き合うのが面倒くさいという方は、飛ばして最後のまとめだけ読んでもらってもかまいません。
1 見渡せば詠(ながむ)れば見れば須磨の秋 桃青
2 桂の帆ばしら十分の月 四友
3 さかづきにふみをとばする雁鳴て 似春
4 山は錦に歌よむもあり 似春
発句は桃青。関西に旅立つ二人のために、須磨の秋を詠んでみせました。藤原定家の「見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮」の本歌取りです。
脇句、発句の「詠(ナガメ)」に対して「月」が付合です。月の定座は百韻の場合7句目ですが、発句が秋の際には第三までに月を出す決まりなのでここで出しました。中国の伝説では月には桂の木(中国ではモクセイを指す)が生えているとされるので、月を舟に見立てて、桂で作った帆柱の帆を十分に張っていると詠みました。
第三、前句の「月」に対し「かりがね」が付合。月見の酒宴、雁が飛んでいくのが見える。その脚には文が結び付けられているであろうか、という句意。前漢の蘇武が匈奴に捕らえられた時、雁の脚に救出を求める手紙を結び付けて送ったという故事に基づきます。
4句目、この酒宴を月見ではなく紅葉見に転じました。人々は紅葉の歌を詠んでいます。
5 ゑぼし着て家に帰ると人やいふ 桃青
6 うけたまはりし日傭大将(ひようだいしよう) 桃青
7 備(そなへ)には鋤鍬魚鱗鶴のはし 似春
8 前ははたけに峰高うして 似春
類船集では「錦」に対し「帰る古里」が付合語になっているのですが(故郷に錦を飾る、の慣用句から)、5句目の「家に帰る」はそれに準じているのかもしれません。山は紅葉の錦で、人は烏帽子で身を飾るのです。
6句目、烏帽子をかぶった日雇い人足の大将が仕事を仰せつかって、その帰り道。
7句目ですが、類船集では「鋤」の付合に「日傭」が挙がっています。ということは、六句目「日傭」から七句目「鋤」への付は「題」⇒「付合」ではなく「付合」⇒「題」という連想になっています。以前見た連歌、「水無瀬三吟」ではそういう逆モーションはなかったのですが、俳諧では普通にあることのようです。
日傭大将は仕事の備えとして鋤、鍬、鶴嘴を置いているよという句意。大将を侍大将になぞらえて、「鶴翼・魚鱗の陣」の口調を滑稽に織り込んでいます。
8句目、「鋤」の付合に「田畑」があるので畑をもってきました。
ここから少し飛ばして、29句目に行きます。二ノ表の真ん中あたりです。
29 狼や香の衣に散紅葉 桃青
30 骸(かばね)導く僧正が谷 似春
31 一喧嘩岩に残りし太刀の跡 桃青
32 処(ところ)立のく波の瀬兵衛(せひょうえ)似春
29句目は「狼に衣」のことわざをもじったもので、狼が香染の衣を着て人に化けている。
30句目、類船集では「骸」の付合に「狼」が出ているのですが、「狼」⇒「骸」の逆モーションの付になっています。
31句目、鞍馬の僧正が谷は牛若丸が武芸の稽古をした場所で、岩に太刀で切りつけた跡が残るという故事に基づく。
32句目、前句の喧嘩はやくざ者の出入りと読み替えて、「波の瀬兵衛」という架空の人物がショバを譲った話ということにしました。
33 今ははやすり切果て飛ほたる 桃青
34 賢の似せそこなひ竹の一村(ひとむら) 似春
35 鋸を挽て帰りし短気もの 桃青
36 おのれが胸の火事場空しく 似春
33句目、「波の瀬兵衛」は今や零落して擦り切れた蛍も同然の姿です。
34句目、蛍は実際に飛んでいるものと見なして、それが竹の一叢に迷い込んでいった。昔の中国に「竹林の七賢」という、竹林の中の室で清談を交わした賢人たちがいましたが、この蛍が迷い込んだのは賢人ぶった偽物がいる竹林。
「蛍」に「庭の若竹」が付合とされます。
35句目、偽賢人はいたって短気なので、鋸で竹を伐って帰っていってしまった。
36句目、短気者が竹を鋸で切ったのは、燃える怒りをしずめるためだったのだが、おかげで胸の中の火事も消えていった。
ここで前句の「鋸」を類船集で調べると、解説のところに「火けし道具に鋸は重宝とぞ」という一文があります。火事が起きると、町火消などは周囲の建物を鋸で切り倒して延焼を防いでいたことがわかります。つまりここでの「火事場」という付は、単に付合語を参照して付けられたのではなく、解説に書かれたような状況を広くイメージした上で考えられているということです。
連歌の場合は、寄合集とは連想される単語・成語を並べたもので、実際それらの語はそのままの形で使用されていたのですが、俳諧の付合は必ずしも特定の語に拘束されず、全体として付合集が示すような情趣を表現できていればそれで良しと考えられました。「日本国語大辞典」で「寄合が用語、題材など形式的なものに関係があるのに対して、(付合は)もっと広く情趣、心情など内容的なものまでをさす」と定義していたのは、このへんの事情を言っていると思われます。
ここからまた飛んで、64句目を読みます。三折表の折端(最終句)から三折裏にかけての部分です。
64 秋を通さぬ中の関口 桃青
65 寂滅の貝ふき立(たつ)る初嵐 似春
66 石こづめなる山本の雲 桃青
67 大地震つづいて龍やのぼるらむ 似春
68 長(たけ)十丈の鯰なりけり 桃青
64句目、この秋、関所は人を通さない。
65句目、「貝ふき立つる」というのは山伏のことなのですが、類船集には「関」の付合として「偽山伏」というのが上がっています。義経の一行が山伏に変装して逃げようとして、安宅の関で止められたという謡曲「安宅」の筋に基づく。このように、「偽山伏」という直接の付合語を用いずに、山伏を暗示する「貝ふき立る」で代替することができるというのが、連歌ではありえない、俳諧ならではの表現です。初嵐の中、物寂しいほら貝を吹く山伏が、関所で足止めを喰らったという句意。
66句目、「石こづめ」とは人を穴の中に入れて、小石を無数に投げ入れて生き埋めにする処刑法。句意がわかりにくいのですが、山伏が石子詰めにされて、その山の麓からは雲が立ちのぼっているということでしょうか?
追記:「石子詰め」について民俗学者の方から貴重な教示をいただきました。山伏の石子詰めというのは、修験道の究極の到達点である「土中入定」を指すそうです。生きたまま土中に埋めてもらい、即身仏としてミイラ化する儀式。桃青さんはそういうこともよく知っていたんですね。
67句目、石子詰めにされたのは実は龍の化身で、大地震とともに龍が雲となって天に昇っていった。
68句目、その龍は実は巨大な鯰であった。ここの付合がなかなか面白いのですが、類船集の「鯰」の項目は次のように記述されています。
鯰[ナマヅ]
刀の鞘 地震 人の肌 瓢箪 池 竹生島 弁才天
近江の湖にはことに大なる鯰のすめるとかや。泥ふかき堀の底におほくすめる物也。神泉苑のの池にも大なる有とぞ。此日本国は鯰がいただきてをるといひならはせり。
前句の「地震」から「鯰」の題が連想されるという、ここも逆モーションの付合です。で、問題は「此日本国は鯰がいただきてをるといひならはせり」の部分で、鯰が地底で地震を起こすという俗信がここで語られています。ですが図像学的に言うと、江戸時代初期までは地震を起こすのは地の底にいる龍だと考えられていたのです。それがどこかで鯰に置き換えられていきました。そして鯰が地震を起こすということを記したわが国最古の書籍は、この類船集なのです(正確に言うと前身の『便船集』にすでに記述があります)。だから芭蕉が「鯰」⇒「地震」という連想をしたということは、彼が類船集を手元に置いて参照していた可能性がきわめて高いことの証拠になると考えられます。
まとめ-芭蕉連句における付合の意味
「見渡せば」の巻の分析から、次のようなことが言えるかと思います。
- 連歌の寄合では「題」⇒「寄合」という連想が中心であったのに対し、俳諧では「題」⇒「付合」と「付合」⇒「題」の両方がある。
このことは、連歌の言語感覚では特定の歌語が題として重視され、その下に寄合がぶら下がるというヒエラルキー構造を持っていたのに対し、俳諧では題も付合も平等な相互関係にあるというフラットな言語観があったと考えられる。 - 連歌の場合は寄合は寄合集に記載してある語彙をほぼそのまま利用するのに対し、俳諧の場合は情趣さえ通うなら付合の表現は変えていいとされた。連歌が「形重視」であるのに対し、俳諧は「内容重視」で自由度が高い。
- 付合を利用した句を出しているのはもっぱら似春で、桃青はごく少ない。このことは、芭蕉が付合集に寄りかかったマンネリ発想を好んでいなかったことを示すのであろう。鯰の句をはじめ、桃青にも付合を使った句が皆無ではないので、そうしたやりかたを否定してたわけではないだろうが、採用に積極的ではなかった。こうした芭蕉の志向は、この後の蕉門俳諧の傾向に大きな影響を与えることになろう。
芭蕉と付合(寄合)の関係については、もう一度続きを書くつもりです。
『俳諧類船集』の原文を読みたいという方は、『連珠合璧集』同様に「日本文学Web図書館 和歌・連歌・俳諧ライブラリー」に全文が収録されています。