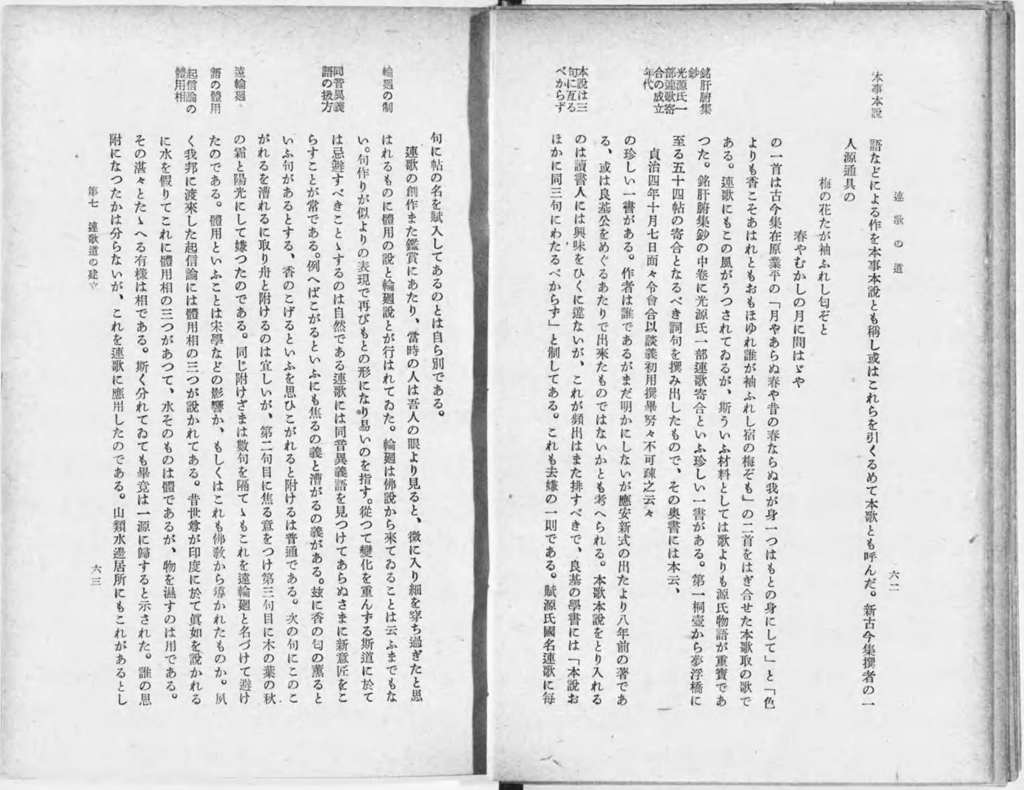(「国文学言語と文芸」4(1)、1962)
「体」と「用(ゆう)」とは何か
連歌新式の次の項目は非常にややこしい。式目を理解する上での最難関でしょう。さいわい永山勇先生は「連歌における体・用(ゆう)の説」(「国文学言語と文芸」4(1)、1962)というすぐれた論考を発表されています。これを参考にします。
まずは式目の現代語訳を見てみてください。
「体」と「用(ゆう)」について
「春」を詠んだ句に「弓」と付けた場合、さらに次の句では「引く」「帰る」「押す」などという語を付けてはならない。これらの語は〈用〉であるからだ。「本」「末」などの語なら付けてよい、これらは〈体〉であるからである。打越に〈体〉の語があった時は、「本」「末」を付けてはならない。
「長」を詠んだ句の次に「縄」を詠んだ場合、さらに次の句では「短」を詠んではならない。これらすべてが〈体〉になってしまうからである。「繰る」「引く」などだったら、これは〈用〉であるから付けてもよい。
「春」の句に「弓」を付けるとはどういうことでしょうか。これは、「春」は「張る」と同音意義語なので、その連想で「弓を張る」を想起し、付句で「弓」を描いたということなのです。掛詞(かけことば)を利用した付けです。
さて、ここで〈体〉と〈用〉ですが、物本来を示す語が〈体〉、その機能や様相を示す語が〈用〉となります。そうすると「張る」は弓の機能を示す語であるから〈用〉、「弓」は物本体を示すから〈体〉である。
ここで気をつけるべきは、「春(張る)」という語自体には体とか用といった特性はないということです。あくまで付句の「弓」との関係性によって〈用〉という性格が生まれる。
次の付句では、前々句の打越を避けるためにここには弓の〈用〉の語を持ってきてはならない、〈体〉を持ってこなくてはならない。「引く」「帰る」「押す」などは弓との関連で〈用〉を示すからここには持ってこれない。「弓を引く」「返し弓」「(弓の)押手」などの概念があるから、これらの動詞は弓の縁語であり〈用〉を示すのだ。
このへんまではわかりやすいでしょう。そして、ということは〈体〉とは体言(名詞など)で、〈用〉とは用言あるいは修飾語のことだなと早とちりする人がいるかもしれません。しかしコトはそう簡単ではない。
「春(張る)」→「弓」と来た次に、「本」「末」なら付けてよいという。弓の下部が「本」、上部が「末」と呼ばれ、これらも弓の縁語なので、付句に使用できる、これらは〈体〉を示す語だから「春(張る)」の〈用〉とは打越を嫌わないというのです。
まずこのへんでイライラする方がいるでしょう。「弓」に対して「春(張る)」「引く」「帰る」「押す」「本」「末」の6語が縁語であるなんて、いったいどこを調べたらわかるんだ--とむしゃくしゃするかもしれません。
それについては、連歌寄合書を見るのが参考になります。何度か紹介してきましたが、一条兼良の『連珠合璧集』は連歌の連想語をリストにしたもので、これを見ると単語の連想関係がわかってきます。試みに「弓」を引いてみると次のようなものが連想語として挙がっています。
引 本 末 いる はる そり つる 月 杯のかげ 狩人 武士 馬 あづさ をして(押し手) 高円山
上記の6語のうち5語が縁語として挙がっていますし、残る一つの「帰る」についても、「帰」の連想語を調べると「弓」が挙がっています。『連珠合璧集』は中世言語の連想網を知るうえで非常に貴重な資料だと言えます。
次に、「本」「末」が「弓」に対して〈体〉であるというのはどういうことなんだ、「本」も「末」も弓の一部の様相を指す語であるから、〈用〉ではないのかと疑問を持つ向きもあるでしょう。
それについて説明する前に、「連歌における事物の分類」ということについてお話ししたいと思います。
連歌における事物の分類(山類・水辺・居所)
この連載の第2回(百韻の構成、打越と去嫌とは何か)を読んでいただいた方には、連歌の各句の題材が「鳥、木、山類...」などというようにいくつかのカテゴリ(部立)に分類されるということを見てもらいました。題材を分類することで、似通った題材が打越関係で繰り返されないようにチェックしていくのです。
打越が問題とならないように、同種の題材は3句連続で繰り返してはなりません。ところが例外があって、「旅・神祇・釈教・述懐・山類・水辺・居所は三句まで続けてよい」ということになっているとご説明しました。
3句続けてよいとはいっても、打越関係で輪廻が生じてしまうとまずい。それを避けるために重視されるのが、〈体〉と〈用〉の関係なのです。たとえ山類の句が3句続くとしても、打越関係で体と体、用と用が重ならないようにする。それによって変化・展開を作り出すようにしようということです。
連歌新式は事物を19通りぐらいに分類していますが、そのうち「山類」「水辺」「居所」については、何が〈体〉で何か〈用〉かを具体的に例示しています。その分類を以下に表にしてみます。
| カテゴリ | 説明 | 体 | 用 | 体・用の外 | カテゴリ外 |
| 山類 | 山に関する事柄 | 岡、嶺、洞、尾上、麓、坂、岨、谷、島、山の関 | 梯、滝、杣木、炭竃 |
| 岩橋、杉、猿、薪、爪木、滝つ瀬、 |
| 水辺 | 水に関する事柄 | 海、浦、江、湊、堤、渚、島、沖、磯、干潟、岸、汀、沼、川、池、泉、洲 | 波、水、氷、塩、氷室、清水がもと | 浮木、舟、流、塩焼、塩屋、水鳥類、蛙、千鳥、杜若、菖蒲、蘆、蓮、真菰、海松、和布、藻塩草、萍、海士、閼伽結、魚、網、釣垂、筏、手洗水、懸樋、下樋 | 砂、苫屋、霞の網、鶴、鷺、螢、小田返す、布曝す |
| 居所 | 住居に関する事柄 | 軒、床、里、窓、門、庵、戸、枢、甍、壁、隣、垣 | 庭、外面(とのも) | | 栖、住居、花のあるじ、露のやどり、簾、筵、懸樋 |
(肖柏の改訂版は記述を省略していて対比がわかりにくいので、連歌新式の原形の一つである『連理秘抄』を参考にして欠落部を青字で埋めてあります)
先に、〈体〉と〈用〉はことば同士の関係性によって決まるので、「春(張る)」という語自体には体とか用といった特性はないと言いましたが、これら3ジャンルについては式目でそれぞれの語の体と用を決めてしまっています。
これらの規定を参照して、永山勇先生は体と用とは何かを解説しています。先生は〈体〉、〈用〉、〈体・用の外〉をそれぞれ次のように定義します。
- 「体」とは、その物の実体、形体の一部分、(属性・形状・性質をも含む)あるいは相伴なって離れない関係や永続性を有するものであって、最も関連性が深いもの。
- 「用」とは、流動性を有するもの、一時的な、臨時的、附加物的な関係のもの、したがって変化し易いものであって、体よりは関連が浅いもの。
- 「体・用の外」とは、用よりさらに関連が疎遠なもの。(非山類物、非水辺物、非居所物をも含む)
最初の式目の記述に戻ると、「弓」に対してその「本」「末」は、実体・形体の一部分であり永続性を有するから、体であるということになります。一方「張る」「引く」「帰る」「押す」は一時的・臨時的な機能であるから用になります。
さらに、「縄」について「長い」「短い」というのは実体そのものの形状であるから体、「繰る」「引く」は一時的・臨時的な機能であるから用とされます。
3句の並びを「体体体」「用用用」「体用体」「用体用」というようにすると、打越と付句の機能が同じになってしまう。打越と付句は異なる機能にしなければならないというのが、この条項の意味するところです。
表の山類、水辺、居所の区分ですが、たとえば「岡」が体で「梯(かけはし)」が用であるというのはわかる。前者は実体で後者は附加物であるからです。しかし「洞」が体で「滝」が用だというのは理解しづらい。両者ともに山の地形じゃないか、どう違うんだと突っ込みたくなります。実際、これらの体と用の区分は時代により、式目により食い違っているのです。永山先生も「体・用の識別は、心理的なものであり、観念的なものであり、またおのずから主観的なものたらざるをえない」「関連の親疎・深浅という以上、そこに客観的基準というものを確立することは甚だ困難」と認めています。
〈体〉と〈用〉の区分はかなり便宜的なものだと言えるでしょう。
どちらにも区分されない〈体・用の外〉は、同一カテゴリではあるけれども打越を気にせず使用してよい題材。
〈カテゴリ外〉はそもそもその分類に含まれないもの(非山類物、非水辺物、非居所物)であるから、体・用に関して打越が問題になることはない。ただし、例えば山類から非山類に移ったら、次はもう山類に戻れない(山類の打越になるから)ということになります。
実例を一つ見てみましょう。飯尾宗祇らの『水無瀬三吟』(1488)より、脇句から第四までを引用します。
行く水とほく梅にほふ里 肖柏
川かぜに一むら柳春みえて 宗長
舟さすおとはしるき明がた 宗祇
「行く水」「川かぜ」「舟さす」と水辺が3句続くのですが、「水」は〈用〉、「川」は〈体〉です。では「舟」はといえば、〈体・用の外〉ですから、これは気にしなくてもよいということです。
ところが他の式目書では「舟」を〈用〉にしてある場合もあるのです。そうなると「水」の〈用〉と打越が嫌うことになってしまってまずいですね。こんな具合で、体と用の区分は結構危ういところがある。
その他の事物の分類
「連歌新式は事物を19通りぐらいに分類している」と述べましたが、山類・水辺・居所以外の16ジャンルも一覧表にしておきましょう。これらのジャンルについては体と用の区分は記述されていません。実際問題として、体と用の関係が問題になるのは、使用頻度の高い上記3ジャンルに限られていたということでしょうか。
具体的な用語の例は連歌新式では一部を除き系統立って挙げられていないので、『連珠合璧集』や『無言抄』(応其編、1603頃)の分類を参照して青字で補足してみました。
| カテゴリ | 説明 | 用語の例 | カテゴリ外 |
| 人倫 | 人間に関する事柄 | 人、我身、友、父、母、誰、関守、主、独、媒、親子 | 月をあるじ、花をあるじ、僧都、山姫、木玉、ふたり |
| 旅 | 旅に関する事柄 | 旅、宿、中宿、便の文 | |
| 神祇 | 神社や神に関する事柄 | 神、社、鳥居、しめ、ぬさ、夏祓、野宮、神楽、下照姫、など | |
| 釈教 | 仏教に関わる事柄 | 仏、御名、寺、法、尼、弥陀、弥勒、鶴の林、あか水、罪、など | |
| 述懐 | 世に生き永らえることの辛さを述べること | 世、墨染、命、玉の緒 | |
| 懐旧 | 昔を懐かしむ心情 | 老、思い出、古、昔 | |
| 無常 | 死や葬送に関わる心情 | 霞の谷、塩干山、かへらぬ道、ながき別、無名の煙、古枕、古衾 | |
| 恋 | 恋愛に関すること | 恋、思、涙、書、名、待心、逢心、別心、面影、独寝、恨、など | |
| 光物 | 天体として光るもの | 月、日、星 | |
| 降物 | 空から降るもの | 雨、露、霜、雪、霰 | |
| 聳物 | 空にたなびくもの | 霞、霧、雲、煙 | |
| 名所 | 詩歌に詠まれる著名な場所 | (多数) | |
| 植物 | (「草」と「木」に分かれる場合も) | 若草、竹、竹の子、篠、若菜、杜若、菫、山吹、藤、葵、あやめ、まこも、蓮、撫子、夕顔、萩、女郎花、朝顔、葛、荻、すすき、菊、菅、浅茅、蓬、浮草、玉藻、忍草、蘆、葎、なのりそ、みるめ、瓜、若木、老木、朽木、ははきぎ、梅、桜、花、柳、李、卯花、橘、紅葉、桂、松、槙、椿、杉、柏木、榊、柴、その他多数 | |
| 生類/動物 | (「鳥」「獣」「虫」「魚」「貝」などに分かれる場合も) | 鳥、百千鳥、鶯、ほととぎす、雁、雉、雲雀、燕、鶉、鴫、千鳥、鴨、鶏、烏、雀、鷲、鷹、山鳥、鷺、都鳥、鹿、馬、駒、牛、犬、猿、虎、狐、虫、松虫、鈴虫、きりぎりす、蟬、空蝉、螢、蛙、蝶、ささがに、龍、魚、鮎、亀、貝、その他多数 | |
| 衣裳 | 衣服に関すること | 衣、袖、唐衣、きぬた、衾、帯、綾、糸、綿、布など | |
| 夜分 | 夜の風景 | 螢、蚊遣火、筵枕、床、又寝、神楽、夕闇、いさり | |