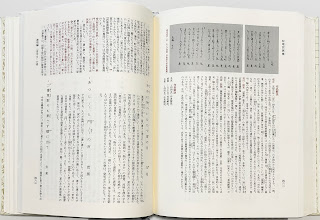来之の連句
1790年の来之編「春興集」から、来之一門の連句を読んでみましょう。正月の顔見世ということで、全員が一句ずつ付け、付け終わった24句目で終了としています。
1 うぐひすや夜は梟梅の月 来之
2 ふまぬ垣ねの雪のむら消 秋水
3 陽炎にいとけの車さしよせて 花竺
4 膝にはらりとこぼす別飯 芹水
5 かほり来る桧原おろしの折々に 雪馬
6 海岸遠く鐘かすかなり 雅石
来之の発句は「鴬」に「梅」の配合で、もうベタベタに月並です。ですが以前のブログで説明したように、井原西鶴は「梅に鴬、松に雪、藤に松、紅葉に鹿、花に蝶、水に蛙というような決まった付けをするのが正しい道である」 と言っている。月並が良いという考えなんですね。関西では西鶴のような俳諧観が根強く残っていたと見るべきでしょう。こういう状況を見て芭蕉は「京都大阪では蕉風は根付かないなあ」と嘆いたわけですし、吉分大魯は「芭蕉を復興させるぞ~」と紋切型を排し、自分の実体験に基づく俳諧を実現しようとしたのでした。
古俳諧というのは、芭蕉や蕪村といった大作家の句だけを見ていたのでは、彼らが何を改革しようとしたのかがよくわかりません。来之のようなマイナーポエットの句も読んでこそ改革の意味がわかるというものです。
第三では子ども用の牛車が垣根近くに寄せられます。4句目、これは若様が養子に出されようとしている状況で、別れを悲しんで子は膝にご飯をこぼしてしまいます。
7 綰柳の詩をさまざまに作りなし 松波
8 横川の室へ艾まいらす 眠花
9 ありふれた品を小重に取あはせ 素流
10 やはらかものをまいどいたゞく 錦車
11 大せつな御主を忍ふ我恋は 羅扇
12 きへもやりたき霜の足跡 仙國
7句目、「綰柳」というのは、中国では親しい人との別れにあたっては柳の枝を輪にして送別する風習があった。そのような別れの詩をいろいろに作っている。1~3句目が春の句であったのに、6~8句目でまた春に戻ってしまうのは、正月の連句であることを意識したのでしょうか。
8句目の「横川の室」は源氏物語の宇治十帖を意識した表現。作者の眠花はこの中で唯一の女性です。
11~12句目は恋の座。このあたり、歴史的かなづかいに怪しいところが散見されますが、昔の人はけっこうおおざっぱです。
13 野烏の有明月に啼さはき 梅風
14 餓民をすくふ一倉の粟 鷺郷
15 こと腹を出てかしこき君なれや 故園
16 神人(じにん)が公事の時得てしかな 蓬雨
17 斧入て進(しんず)るにあき花の山 秋虹
18 長い羽織は誰も着ぬ春 巴山
13句目はカラスが鳴き騒ぐ不吉な情景。はたして14句目で飢饉が到来しますが、為政者の賢明な判断により粟が放出されます。15句目、嫡出のお世継ぎが退いて、異腹の兄弟が殿様になり、賢い判断をなさった。16句目、殿様が賢い人に代わった機会を逃さず神社の人が裁判を起こす。17句目、裁判に勝って山の所有が認められ木を伐っているが、それにも飽きてきた。このへん、また春に逆戻りです。
19 たま/\の御影供休に飛出行 移石
20 女房もてとて伯母のうるさき 漢水21 薄いものあとまで見ゆる秋の月 驢丹22 小刀添し盆の御所柿 百長
23 次の間は皆昼酒に酔たふれ 春山
24 とう/\と鳴滝殿の滝 竹之
19句目、御影供に参るため思いがけず店が休みになったので、使用人は実家に戻ろうと飛び出していく。20句目、実家に戻ったものの伯母さんから説教。
芭蕉時代の連句は解釈が難しく、評釈書に頼らないとなかなか理解できないのですが、安永・天明期以降になるとかなりわかりやすくなっています。とくに来之一門の連句は、良くも悪しくも飛躍が少ないので読みやすいと言えるでしょう。
撰集に採られた句
来之の発句は同時代に編まれたいくつかの撰集に採録されています。まずは黒柳維駒(これこま)編の「五車反故(ごしゃはうぐ)」(1783)より。維駒は蕪村の高弟であった黒柳召波の息子です。父の十三回忌の追善として刊行したもので、もともと召波が集めていた撰集に維駒が最近の句を補足して完成させたもの。
野の宮や笹の古葉の落る音
嵯峨野の野宮神社あたりの竹林を、そのままに描いた句。
次は西村呂蛤編の「雁風呂」(1792)より。呂蛤は几董門下で、几董没後、夜半亭四世を継ぎました。こうやって見ると、来之は几董、維駒、呂蛤と蕪村系の俳人たちと比較的よく付き合っていますね。蕪村自身も一度、来之の「春興集」に句を寄せたことがあります。来之と蕪村一門では俳諧観が合うとは思えないのですが、だいたい今日でも関西の俳人たちには関東と違って流派の垣根を越えて自由に付き合う気風があります。几董はとくに人当たりがよくて広く交際できる性格でしたから、来之とも行き来できたことでしょう。
卯の花を血になよごしそ郭公(ほとゝぎす)
筆柿の紅葉見事や光悦寺
「ほととぎす」と「卯の花」は付合。そして「啼いて血を吐くほととぎす」という定番の言いまわしに従っていますね。「筆」と「柿」も付合。来之らしい徹底的に紋切り型を目指した句です。
もう一つ、蝶夢編の「新類題発句集」(1791)より。蝶夢は蕉風俳諧の復興を願って芭蕉一門の俳諧の集成などに努めた人で、従来の発句を季語別に収集した「類題発句集」を編纂しましたが、続いて当代の作品を集めた「新類題発句集」を刊行したのでした。
そめて行一むら雨やかきつ機葉桜や寺行ぬける人ばかり茅の輪から秋にし生るゝこゝろかな岩橋の明ゆく顔や煤はらひ
一句目は「そめていくひとむらさめやかきつばた」と読みます。雨の菖蒲園を美しく詠じました。二句目は、桜の時節は皆足を止めて花に見入っていたけれど、葉桜のころともなれば誰もが目を向けることなく寺を通り抜けていくよという句。実感があって私はわりと好きな作です。四句目、「岩橋」というのは葛城山に石橋を架けようと一言主の神に命じたところ、顔が醜いので夜しか働こうとしなかったという伝説を踏まえます。煤払いが終わって顔が汚れて真っ黒になっているが、あたかも一言主の神が夜の仕事を終えたときの顔みたいだねと言ってみた句でしょうか。
本法寺界隈を歩く
さて、20年前に冬野虹が死去した後、私は分骨して遺灰を本法寺にも納めることにしました。彼女が大好きだった姉と同じ場所に葬ってほしいと思っていたことは間違いないからです。
この8月も、私は虹のために本法寺の共同墓にお参りし、また来之ゆかりの土地を訪ねてきました。
共同墓に花と線香を供えたあと、今は参る人とてなさそうな来之の墓にも線香をおすそ分けしてきました。墓石の向かって左側面には、彼の時世の句が彫られています。
今日までは世耳つとめたる案山子かな
「世耳」とは「世辞」のこと。自分のことを「案山子」と嘲り、生きている間は周囲にお世辞を言いながら身過ぎ世過ぎをしてきましたが、墓の中に入ったらもうその必要はありませんという遺言です。こうした偉ぶらない、世の中を醒めた眼で見ながら少し悲しい気持ちを抱えて人生を送った春鷗舎来之という人物に、いささかの共感の念を持つのは私だけでしょうか。
本法寺に隣接するのが表千家の不審菴と裏千家の今日庵です。この地域は日本の茶道の中心地で、茶道関係の会館や商店を見ることができます。前回、古木町には茶道関係者が住んでいたと書きましたが、これは古木町が不審菴や今日庵に近いことに理由があるでしょう。
来之の住居があった小川通今出川上ルのあたりにも行ってみました。古地図と比べると町の区画が変わっていて、小川通も今出川通もずっと大きな道に変貌していました。本法寺からは歩いて8分ぐらいで、彼がこの寺に葬られたのも自然なこととして理解できます。ひょっとして「早川」という家がないかどうか、道沿いの表札を見て歩きましたが、没後200年以上を経てそんな家が残っているはずもありませんでした。
近くに小さな地蔵堂がありました。この古いお地蔵さんは来之のことを知っているかもしれませんね。
私は天国だの来世だのといったものの存在を信じていませんし、人間の意識は生きている間がすべてだと考えています。しかし「もしあの世というものがあるとしたら」と想像してあれこれ楽しむのは、生き残った者の権利でしょう。私は天上で来之が捌として連句を巻き、そこに冬野虹が参加している様子を思い浮かべます。虹が提出する奇抜な付句を見て、来之は目を白黒させているだろうなあ、そんな光景を空想してほほえむのです。
* * *
本法寺では本阿弥光悦が作庭した「巴の庭」を拝観することができます。また涅槃会のころには長谷川等伯筆の涅槃図が公開されます。もし西陣あたりを観光で訪れることがあれば、よかったら本法寺にもお立ち寄りいただき、共同墓や来之の墓にもお参りくだされば嬉しく存じます。